新日本婦人の会 大阪狭山支部
女性の幸せ・ジェンダー平等のために


10月7日、「なぜ実現しない選択的夫婦別姓」をテーマに
学習会を開催。婚姻における現在の制度として憲法24条では個人の尊厳と両性の本質的平等が書かれているが、民法と
戸籍法で、夫婦同姓制度が強制されている事を学びました。
同姓を強制されるという事は、人格権が侵害される事で、
人権に関わる問題なのだという講師の方のお話に、「そうなんだ! 人権が否定される事なんだ!という新たな気づきも
ありました。
選択的夫婦別姓制度を実現するためには、やはり
国会での力関係を変えないと!
私達がもっと周りに知らせて、人権を大切に
する議員を増やし、国会での多数派となるよう
働きかけ続けていく事が重要なのだと気持ちを
新たにした学習会でした。
5月31日、第69回大阪母親大会が開催され、オン
ラインを含め910人が参加しました。「抑止力で戦争
は止められない。憲法9条を世界に広めよう」のテー
マで、多彩に展開されました。
ミニ学習会として「大阪市をよくする会」から
万博・カジノをめぐる情勢が報告され、府民からも
「万博に職員が動員され、本来の仕事ができない。」
の声、万博遠足させたくない保護者の願い、市民の力で万博遠足をストップさせた運動等の現状報告や取り組みが発表され、交流しました。
次にイスラエル出身のダニー・ネフセタイさんの記念講演がありました。イスラエルの徴兵制による空軍入隊経験を通して洗脳教育に気づき、退役の旅で訪れた日本で初めて日本国憲法の戦争放棄、9条の素晴らしさに気づいた事、日本に住み家具作家となり、平和運動を進めているというお話に納得! 教育の大切さ、人権は幸せになる権利、軍事力ではなく外交の力で犠牲者を出さないと
締めくくられ、会場が一体となり思いを共有しました。
最後に、戦争は止められる事に確信を持ち、私達の願いが実現できる政治につなげようと大会決議を採択。充実した大会でした。





ミモザの花咲く3月8日は国際女性デー。
女性の地位向上と男女平等、平和を願い、
全世界で「女性デー」の行事が開かれて
います。
2025年の国際女性デー大阪集会は、
3月7日に女性団体から360名の参加で
開催されました。
オープニングは、被団協のノーベル平和賞受賞を祝ってのうたごえで始まり、記念講演は、世界で
活躍中の辛淑玉(シン・スゴ)さんの「鳥観図で見る日本社会」 ー他の国々との比較をしながら
日本社会の今を考えるー のテーマで、アメリカやドイツで体験された事例を参加型で講演され、
分かり易いお話でした。
アメリカの運転免許取得では、20ヶ国以上の母国語で試験が受けられる、多様な対応がされている
とか。また、アメリカの天気予報に日本の基地が出てきたり、基地へはパスポート無しで行けたりする
等、日本の基地がアメリカの国扱いされているようでした。トランプ政権になり心配との話には共感!
ドイツでは、子どもの頃より、自分の主張がはっきり表現できる事を大切に教育されているそうで、
暗記中心の日本とは違う等、日本のおかしさを再度発見した講演でした。その後、新日本婦人の会を
はじめ、女性10団体のタペストリーやバナーが次々登壇し、それぞれの団体の決意表明で、会場の
連帯感がわいた集会でした。

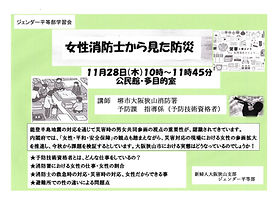
11月28日、2024年の学習会は、女声消防士さんにお話を
してもらいました。まずは、消防署の仕事の話から、ジェンダー視点での防災の事。
例えばAEDの使用について、子どもから大人になるにつれて、女性の救命率が低くなるという数字に驚きました。女性が倒れた場合、救助者が男性だと、女性の衣服を脱がせる事に躊躇して、AEDが使えない事が多いので、救命率も下がるというわけです。
私達は、周りを囲んで隠してあげるとか、衣服を
かけてあげるとか、その場にいてできる事がある
はずだと学びました。
能登半島地震の避難所の様子も聞きましたが、
プライバシーを確保しても、それがDVや性犯罪を
見えなくする事もあると知りました。
もしもの避難所生活の時、ジェンダー視点での
運営ができるように、何ができるか考えようと
思いました。
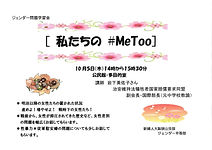

10月5日、ジェンダー平等部の学習会。
日本のジェンダーギャップ指数が世界146ヶ国中125位という人権の後進国なのはなぜなのか?その原因はどこにあるのか?を学びました。明治憲法の下で自由、平等を求めて闘った若い女性達がいた事、彼女たちは女性で
あるがゆえに二重三重の弾圧や拷問を受け、その多くは特高によって殺されています。その女性達の闘いもあって、日本国憲法には人権について明記されていますが、今も続く治安維持法体制で、日本に人権尊重の風は吹いていないとの事。戦後、特高官僚は公職追放、とは名ばかりで、教育委員長や文部次官、文部大臣にまで名を連ねていた事を知りました。日本人の人権意識の低さはここにも原因があったのです。自由、人権、平和を求めて闘った先輩達の遺志を受け継ぎ、これからも声をあげていかなければ、と思いました。国連NGOの新婦人だからこそ。
2022年の日本のジェンダーギャップ指数は146ヶ国中116位と主要7か国中
最下位となりました。日本の実質賃金は、4半世紀で約1割も下がっています。
平均賃金もOECD加盟国35ヶ国中22位と、韓国と比べて3万円も低く、年収
200万円未満の労働者の割合がこの10年間で倍増し、特に女性は賃金が低く、
失業や休業で住居さえ失う困窮状態に陥っています。
女性が、社会における構造的な差別(賃金や年金、学業の男女
格差、家事労働やケア労働分担等)を受けず自立できていれば
苦しむこともなかったと思われる事が数多く見られます。
ジェンダー平等社会実現のため、男女の賃金格差を是正し、
女性も男性も1人1人が自立して生活できるように、賃金、社会
保障の仕組みを一体のものとして変えていく必要があります。
そして、全ての労働者が仕事と生活が両立できるように、賃上げと労働時間短縮を実現していかなければ
なりません。1つ1つの問題に取り組み、声をあげていきましょう。
.jpg)

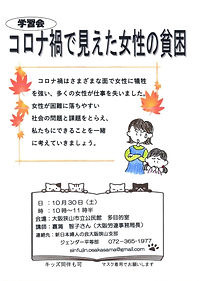
10月30日、大阪労連事務局長に、女性の働き方、働かせ方…
「コロナ禍で見えた女性の貧困」と題して講演して頂きました。
資料の「ジェンダー平等ガイドブック」で、数字で分かりやすく説明
されました。
コロナ禍は雇用に深刻な影響を与え、関連の失業者は11万人。非正規
労働者、女性、若者等に痛みが集中しています。それ以前から低賃金、
不安定雇用が続き、年収200万円以下のワーキングプアは、15年連続で
1000万人を超え、最低賃金で働く人の割合がここ10年程で倍増。介護、
保育等低賃金で働くケア労働者に女性が多く、女性が多い職業は賃金が
低い。この事は、「ジェンダーギャップ指数2021」で日本が世界156ヶ
国中120位となっている事にも表れています。
コロナ禍で女性の雇用劣化や、DV、自殺の急増が浮き彫りになりました。今こそ雇用差別や、低賃金の非正規労働者の在り方を変える事が重要です。「1人の仕方ない」から、「みんなで
変える」に、声をあげていきましょう。発言者も多く、中身の濃い学習会でした。
2020年のジェンダー平等部学習会には26名参加(男性3名)、時間が足りないくらい質問や意見が出て、事後のアンケートにも多数の回答があり、関心の高さがうかがえました。
憲法13条には「すべて国民は個人として尊重される」と明記されています。講師から「法律で夫婦同姓を強制している国は日本だけ、約96%が夫の姓を名乗っている。それには日本の文化の歴史がある。」等のお話がありました。
「歴史的経過も含め、この問題を初めて学びました。」
「個人の尊重が1番の眼目。」「日本では個人の尊重という考えが弱いのでは?」等の感想が寄せられました。
今話題の問題に取り組み、考えを深める事ができました。

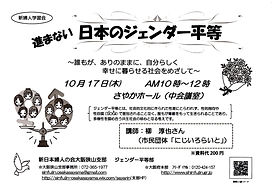
10月17日、2019年のジェンダー平等部の学習会を行いました。7年間の積み重ねで、やっとこの問題が解りかけてきたように思います。近年、若い方達の中で、ジェンダー平等への関心も高まってきているようです。
大阪狭山市でも、行政の中で、提出書類に男女別覧を無くすとか、同性婚を認めていく等の方針を出させていく活動を強めていきたいです。
2018年の学習会のテーマは「セクハラと日本社会」。先生の素晴らしいお話、グループ討議等、とても良かったです。昔に比べ、少しずつの変化は見られ、いろんな方が勇気を持って次々カミングアウトされているのもいい事だと思います。でも安倍政権の中枢で未だに女性に対する偏見や差別が多いのはなぜでしょう。日本の社会は、本当の民主主義の歴史がまだ浅いのかもと思ってしまうのですが…。世界では、先日台北で約14万人参加のLGBTパレードが行われたと報じられ、驚きです。マイケル・ムーア監督が「日本人は文句を言うが、

なかなか行動に移さない。」と言っています。文句を言っているだけでは世の中変わらないよ、もっと行動を起こそうと言いたいのでしょう。10月の事務所カフェでも、学習会の感想も含め、自分の体験等自由に話し合いました。
日本における男女差別、考え方が世界的に遅れている中で、人間として認め合い、大切にされるようさらに声をあげ行動していきましょう。

2017年のジェンダー平等についての学習会のテーマは、「女性と貧困」。日本はOECDの中で子どもの相対的貧困率がワースト1になったそうです。これだけ物があふれ、豊かに見える日本がなぜ? デンマークはベスト1。同じ資本主義国の中でこんなにちがうのはなぜ?
日本が大企業とアメリカを優遇しているのと比べ、デンマークは企業で働く人達を大事にするルールを作っているからではないでしょうか。そして人、特に子どもは国の宝であるという考えがもとになっているようです。
日本国憲法でも、25条で全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとされています。この素晴らしい憲法を生かす政治を実現していかなければならないという事がよく分かった学習会でした。
�ここ最近、LGBTが新聞やテレビなどで話題になっています。多様な性のあり方を知ることは、それを理解することにつながるのだと思います。
ジェンダーを考えることは、何がこの社会で支配的な考え方なのかをあぶりだすことであり、支配的言説は、「あたり前のこと」「常識」「自然なこと」などではなく、人間によって作られたものであることを自覚することにもつながります。
LGBTの学習会は難しいと思っていたのですが、たくさんの方に感想文を書いて頂き、開催してよかったと思いました。

「介護」から見るジェンダー平等

2015年10月29日の学習会は20人参加で行われました。とても中身の濃い学習会でした。ほとんどの参加者が今現在介護していたり、過去にしていた方でした。介護はもはや嫁の仕事ではなくなり、夫や息子が担う時代になってきている。親の介護のために仕事を辞めて、介護を担う人が増えているという話、衝撃的でした。
日本の介護は一体どうなっていくのか?公的責任の回避、民間資本の導入、国庫負担を減らしたお金でオスプレイを5機買うとは!こんなひどい国あるでしょうか?怒りがわいてきました。政治を変えないと、どんどん改悪される、と思った学習会でした。
2014年9月25日、ジェンダーフリー学習会を持ちました。市の人権広報
グループの方を講師に招きましたが、大阪狭山市の実情が資料(第3期大阪
狭山市男女共同参画推進プラン、小中学生にとったジェンダーについての
アンケート結果など)で具体的に示されていてわかりやすかったです。
聞くだけではなく、そのあとグループでの話し合いを持ったのも、
一人ひとりの思いが出せ、良かったのではないかと思いました。
男女が共に大切にされる社会こそ、真の意味でのジェンダーフリーになるという事でしょうか?
いろいろ勉強し、とても良かったです。
